はじめに|PM初心者の私が学んだ「ユーザーの声を聞く大切さ」

現在、社内のリスキリング制度を活用してプロダクトマネージャー(PM)に挑戦中です。
学び始めたばかりの頃、私は開発チームの会議で何度もこんな疑問を感じました。
 たまご
たまご「ユーザーは本当にこの機能を求めているのだろうか?」
「数値はわかるけど、なぜそういう行動をしたのかがわからない…」
アクセス解析やアンケートで数字は見えるのに、ユーザーの本音や行動の理由まではわかりません。
そんなとき、私の先輩PMに教えてもらったのがユーザーインタビューでした。
ユーザーインタビューは、製品やサービスを実際に使うユーザーに直接話を聞き、
- 使いやすかった点
- 使いにくかった理由
- 気づかなかった課題
といった定量データでは見えない「なぜ」を明らかにする調査方法です。
最初は緊張しましたが、たった数回のインタビューでも、数字だけでは気づけなかった改善のヒントが次々と見つかりました。
この記事では、私自身の学びも踏まえて、初心者PMでも失敗しないユーザーインタビューのやり方・質問例・活用事例をわかりやすくまとめます。
この記事を読み終えたら、あなたもきっと「ユーザーの声」を開発に生かす第一歩が踏み出せるはずです。
- ユーザーインタビューの基本と目的
- 初心者PMでも失敗しない実施ステップ
- 実務で役立つ質問例・テンプレート
- 成功事例から学ぶ活用法
- アンケート・ユーザビリティテストとの違いと使い分け
ユーザーインタビューとは?初心者PMがまず知るべき基本
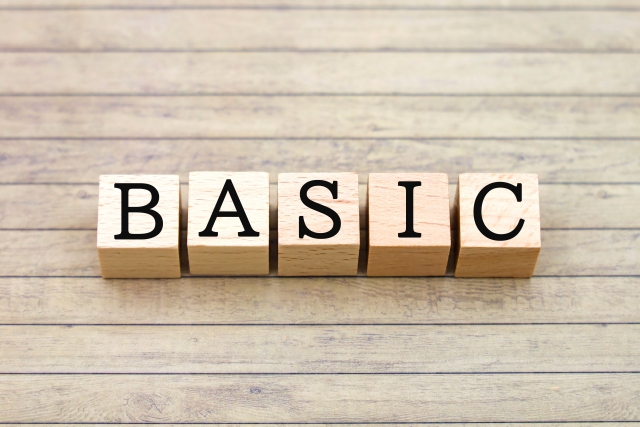
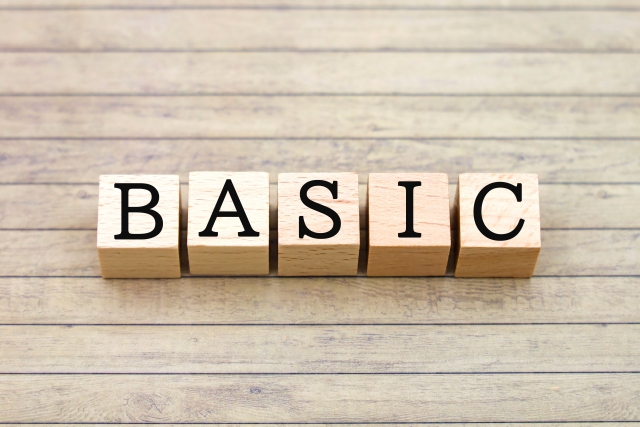
ユーザーインタビューの定義と目的
ユーザーインタビューとは、製品やサービスの利用者(ユーザー)に直接話を聞き、体験や課題を深く理解する調査手法です。
アンケートのような定量調査(数値で傾向を把握する方法)とは異なり、
- なぜその行動をしたのか
- どんな気持ちで使ったのか
- 言葉にしていない不満や期待
といった数字だけでは見えない「本音」や潜在ニーズを引き出せるのが大きな特徴です。
初心者PMにとっての最大のメリットは、定量データだけでは気づけない改善のヒントが得られることです。
ユーザーが本当に困っているポイントや、期待している体験を知ることで、
- 新機能の改善点を明確化
- サービス全体の方向性を検討
- 次の施策の優先順位を決める
といった意思決定に活かせます。
定性調査としての特徴とメリット
ユーザーインタビューは定性調査(Qualitative Research)に分類されます。
少人数でも深く掘り下げられる点が特徴で、主なメリットは次の通りです。
- ユーザーの本音や感情を理解できる
┗ 表情・声のトーン・しぐさなど、数字に表れない情報が得られる - 行動の背景にある理由がわかる
┗ 「なぜ離脱したのか」「なぜその機能を使わなかったのか」を特定できる - 新しいアイデアのきっかけになる
┗ 想定外の意見や潜在ニーズを知ることで、改善や新機能のヒントになる
ユーザーインタビューのやり方|5つのステップで失敗しない進め方
初心者PMがユーザーインタビューを実施する際は、5つのステップを意識するとスムーズに進められます。



この流れを押さえておけば、初めてでも「聞きっぱなしで終わる…」という失敗を防げます。
ステップ1:目的を明確にする
ユーザーインタビューの成功は、最初の目的設定で決まると言っても過言ではありません。
なんとなく「感想を聞きたい」だけでは、会話が散らかり、分析できる情報も得られません。
目的設定の例
また、インタビュー結果をどう活用するか(改善施策に反映・報告書作成など)をチームで共有しておくと、調査の方向性がぶれません。
ステップ2:対象ユーザーを選定・リクルーティングする
目的に沿って、どんなユーザーに話を聞くかを決めます。
条件が曖昧だと、集めた意見がバラバラで分析が難しくなります。
対象ユーザー設定の例
・直近3か月以内に週1回以上アプリを利用した20〜30代女性
・初回利用から1週間以内に解約したユーザー
複数パターンのユーザーを混ぜると、多角的な視点が得られます。
リクルーティング時には、以下を明確に伝えると参加率が上がります。
- 所要時間(例:30分)
- 実施方法(オンライン or 対面)
- 謝礼の有無
ステップ3:質問項目を作る(設計)
質問は、ユーザーが自由に話せるオープンエンド型を基本にします。
「はい/いいえ」で終わる質問だけだと、本音や背景が引き出せません。
質問の作り方のコツ
- 体験の有無 → 頻度 → 直近体験 の順で聞くとスムーズ
- ポジティブ面とネガティブ面を両方聞く
- 具体的な背景を掘り下げる「なぜ?」を用意しておく
質問例
ステップ4:インタビューを実施する
本音を引き出すには、安心して話せる環境づくりが重要です。
インタビュー開始時には、必ず以下を伝えて同意を得ましょう。
- 調査の目的
- 所要時間
- 録音・録画の有無
進行はメモリストに沿いつつ、相槌や追加質問で自然な会話を意識します。



ユーザーの表情や声のトーン、しぐさも観察しておくと、後の分析で役立ちます。
ステップ5:分析・報告で次のアクションにつなげる
インタビューの価値は、実施後の分析と活用で決まります。
- 文字起こしして、発言を整理
- 似た意見・課題をグループ化
- 重要度・頻度で優先順位をつける
分析結果は、改善案やカスタマージャーニーマップ、チーム内の意思決定に直結します。
「聞きっぱなし」で終わらせないことが、ユーザーインタビュー成功のカギです。
ユーザーインタビューの質問例|アプリ・購買体験で使えるテンプレート


「ユーザーインタビューをやってみたいけれど、何を聞けばいいかわからない…」



初心者PMが最初にぶつかる壁は、質問の作り方です。
ここでは、すぐに使える質問例を「アプリ利用体験」と「購買行動」の2パターンで紹介します。
質問は段階的に進めると、自然な会話で本音を引き出しやすくなります。
1. アプリ利用体験の質問例
アプリやWebサービスの使い勝手を知りたいときに有効です。
体験の有無 → 利用頻度 → 直近体験 → 感想の順で聞くとスムーズです。
質問テンプレート例
- 「このアプリを使ったことはありますか?」(体験の有無)
- 「どのくらいの頻度で利用しましたか?」(利用頻度)
- 「直近で使ったのはいつですか?」(直近体験)
- 「特に便利だと思う機能はどこですか?」(ポジティブ面)
- 「逆に、使いにくいと感じた点はありますか?」(ネガティブ面)
- 「そのとき、なぜそう感じましたか?」(背景を深掘り)
ポイントは感想だけでなく理由まで引き出すことです。
2. 購買行動の質問例
商品購入やECサイトの改善に役立つ質問です。
認知 → 検討 → 購入 → 使用後 の流れに沿って質問します。
質問テンプレート例
- 「最後にこの商品を購入したのはいつですか?」(直近行動)
- 「この商品をどこで知りましたか?」(認知経路)
- 「購入前にどんな悩みやニーズがありましたか?」(潜在ニーズ)
- 「購入を決めた一番の理由は何ですか?」(決め手)
- 「他に比較検討した商品はありますか?」(比較行動)
- 「購入後、満足した点・不満だった点は何ですか?」(アフター体験)
この質問セットを使うと、購買プロセスのどこに課題があるかを特定しやすくなります。
質問作成のコツ
・オープンエンド型(自由回答)を意識する
・ポジティブ→ネガティブの順に聞くと話しやすい
・「なぜ?」を必ず入れると、行動の背景がわかる
実務で役立つユーザーインタビュー活用事例
ユーザーインタビューは、実施しただけでは意味がありません。
本当の価値は、得られた気づきをプロダクト改善に反映させることにあります。
ここでは、初心者PMでもイメージしやすい実務での活用事例を2つ紹介します。
事例1:家具メーカーWebサイト改善でUX向上
ある家具メーカーでは、公式Webサイトのリニューアルに合わせてユーザーインタビューを実施しました。
インタビューで出てきた主な意見は次の通りです。
- 「サイトに価格が載っていないので、店頭に行かないとわからない」
- 「自宅に合う家具の選び方がわからない」
この声を受けて、以下の改善を行いました。
- 公式サイトにメーカー参考価格を掲載
- 購入事例やおすすめの組み合わせを紹介するコンテンツを追加
結果、カタログ請求数は199%増、訪問者数は170%増と大きな成果につながりました。
ユーザーインタビューが「ユーザーが本当に求めている情報」を明らかにした好例です。
事例2:ECサイトで潜在課題を発見
あるECサイトのユーザーインタビューでは、表面的にはポジティブな声が多く聞かれました。
「商品の品揃えが豊富で良い」
しかし、会話を深掘りすると、実は次のような本音が見えてきました。
「品数が多すぎて、欲しい商品を探しにくい」
つまり、ユーザーは「多すぎる選択肢」に困っていたのです。
この発見を受けて、サイト内の検索性やカテゴリ整理を改善。
結果として、購入完了率の向上と離脱率の低下につながりました。
このように、ユーザーインタビューは数字だけでは見えない潜在的な課題を発見する強力な武器です。
初心者PMでも、1回のインタビューで思わぬ改善ヒントが得られることがあります。
ユーザーインタビューと他手法の違い・使い分け
ユーザーインタビューは、ユーザーの本音や潜在ニーズを深掘りできる優れた調査手法です。
しかし、他の手法と組み合わせることで、さらに効果的なUX改善やプロダクト改善が可能になります。
ここでは、よく比較される3つの手法との違いと使い分けを解説します。
1. アンケート(定量調査)との違い
アンケートは、多数のユーザーから回答を集めて数値で分析する定量調査です。
一方、ユーザーインタビューは少人数から深い情報を得る定性調査です。
| 手法 | 特徴 | 得られる情報 |
|---|---|---|
| アンケート | 多数の回答を数値化して分析 | 「何が起きているか」がわかる |
| ユーザーインタビュー | 少人数に深く聞く | 「なぜそうなったか」がわかる |
- アンケートで傾向を把握
- インタビューでその理由を深掘り
2. ユーザビリティテストとの違い
ユーザビリティテストは、実際にユーザーに製品やプロトタイプを操作してもらい、使いにくさを発見する手法です。
一方、ユーザーインタビューは過去の体験や行動の理由を深掘りします。
- テストで「この操作がわかりにくい」と判明
- インタビューで「なぜ戸惑ったのか」を深掘り
- 改善施策の方向性が明確に
3. アクセス解析(ログ分析)との違い
Google アナリティクスなどのアクセス解析は、
- ページビュー数
- クリック率
- 離脱率
といった行動データを大量に集められますが、ユーザーの気持ちや行動の理由はわかりません。
ユーザーインタビューで「なぜその行動をしたのか」を補うことで、
定量と定性のデータを組み合わせた信頼性の高いインサイトが得られます。
手法は組み合わせてこそ真価を発揮する
- アンケート:何が起きているかを把握
- ユーザビリティテスト:操作上の課題を特定
- ユーザーインタビュー:行動の理由や本音を深掘り



初心者PMは、まずは小さくユーザーインタビューを始め、
定量データやテスト結果と組み合わせることで、改善施策の精度を高められます。
まとめ|ユーザーの声がプロダクト改善の原動力になる
ユーザーインタビューは、初心者PMが最初に取り組みやすく、かつ効果の高い調査手法です。
たとえ少人数でも、ユーザーの本音や潜在ニーズを知ることで、次のような成果が得られます。
- 定量データだけでは見えない課題が明確になる
- 改善施策や新機能のアイデアが生まれる
- チーム全体で「ユーザー視点」を共有できる
最初は緊張するかもしれませんが、1回のインタビューでも必ず発見があります。
ユーザーの一言が、あなたのプロダクトを大きく前進させるヒントになるはずです。
まずは小さく始めて、1人でもユーザーの声を聞いてみましょう。
その一歩が、プロダクトを成長させる大きな原動力になります。



コメント