はじめに
現在、社内のリスキリング制度を活用してプロダクトマネージャー(PM)に挑戦中です。
新規アイデアを事業に育てる過程で、必ずと言っていいほど耳にするのが「リーンスタートアップ」という言葉です。
一方で、最近のPMコミュニティやSNSでは「リーンスタートアップはもう時代遅れでは?」という声も目にするようになりました。私自身も、初めてMVPを社内で試したときに「本当にこのやり方でいいのだろうか?」と不安に思った経験があります。
この記事では、リーンスタートアップが時代遅れと言われる理由と、2025年の実務でどう活かせるのかを、最新の知見と実体験を交えて解説します。スタートアップだけでなく、企業内PMの方にも役立つ内容を目指しました。
- なぜ「リーンスタートアップは時代遅れ」と言われるのか
- 2025年のPM実務でリーンが通用する場面・しない場面
- 成功・失敗の実践事例とそこから得られた学び
- リーンを進化させるための最新チェックリストと実践ポイント
このあとの章では、リーンの限界と活用術を具体的な事例とともに解説していきます。
リーンスタートアップ時代遅れ論争とは?
リーンスタートアップは、2011年にエリック・リース氏が提唱したスタートアップの成長手法です。
「小さく作って素早く検証する(Build-Measure-Learn)」というシンプルなサイクルで、
大きな投資をする前にユーザーの反応を確かめることができます。
私もPM学習を始めた頃、まず学んだのはこのリーンの考え方でした。
実際に社内で小規模なMVP(最低限の実用的なプロダクト)を作り、ユーザーに試してもらったとき、
「机上で考えていた機能の半分はいらない」とわかったのは衝撃的でした。
しかし近年、このリーンスタートアップに対しては
「スピード重視すぎて、今の市場では通用しないのでは?」
「時代遅れの手法になりつつある」という意見も聞かれるようになっています。
その背景には、以下のような変化があります。
- プロダクトの品質や安全性への要求が高まり、未完成のMVPでは信頼を失うリスクが増えた
- AIやディープテックなど、開発コストが高い領域では小さく作ることが難しい
- SNS全盛時代で、初期ユーザーの不満がすぐ拡散するリスクがある
こうした市場や技術環境の変化が、「リーンスタートアップ時代遅れ論争」を生み出しています。
次の章では、なぜリーンが“時代遅れ”と見られるのかを、より具体的に整理していきます。
リーンスタートアップが“時代遅れ”と言われる5つの理由

リーンスタートアップは、かつてはスタートアップの必須手法として注目されました。
しかし2025年の現在、実務でそのまま適用するには注意が必要です。
ここでは「時代遅れ」と言われる主な理由を5つに整理しました。
1.計画性の欠如とビジョン不足になりやすい
リーンは「小さく作って学ぶ」ことに重きを置くため、初期段階では長期ビジョンが曖昧になりがちです。
短期的な仮説検証に終始すると、方向性がコロコロ変わる“ピボット疲れ”を招き、チームが消耗してしまいます。
2.競争激化とブリッツスケーリングの台頭
市場が成熟し、競争が激しい現在では、ゆっくり学習するより一気にスケールする戦略が重視されることもあります。
特に海外では「ブリッツスケーリング(超高速成長戦略)」が注目されており、
MVPでの小さな実験だけでは市場を押さえられないケースが増えています。
3.SNS時代の悪評拡散リスク
リーンの考え方では、未完成のMVPを早く世に出して学習します。
しかし現代はSNSでの情報拡散が一瞬です。
不完全なプロダクトを出すことで、ブランドや信頼を損なうリスクが高まっています。
4.AI・ディープテックなど高コスト領域との相性の悪さ
AIモデル開発やディープテック領域では、
試作にかかるコストや時間が大きく、小さく作って検証することが難しいです。
このような分野では、リーンの「低コストで高速学習」の前提が崩れやすくなります。
5.高度な品質・安全性を要求される市場での不向き
医療機器や金融サービスなど、初期段階から高い安全性や規制遵守が求められる市場では、
未完成品を試すこと自体が困難です。
このような業界では、リーン単体では不十分で、別の品質保証プロセスとの組み合わせが必須です。
 たまご
たまご私も社内でMVPを作ったとき、ユーザーに試してもらう前に「本当にこの品質で出して大丈夫か?」と議論になりました。
この経験からも、2025年のリーン適用には慎重さが必要だと感じています。
次の章では、逆に今でもリーンが有効に働く場面を整理します。
いまでも刺さる!リーン手法が有効な4つのケース
リーンスタートアップは万能ではありませんが、
2025年でも適切な状況を選べば大きな効果を発揮します。
ここでは、実務で特に有効な4つのケースを紹介します。
1.BtoBやクローズド市場でのMVP検証
エンタープライズ向けの業務システムなど、限られた顧客だけが使う環境では、
初期段階で限定的にMVPを試すことが可能です。
社内システムや実証実験(PoC)でも、少人数のユーザーで改善を重ねるリーンは非常に有効です。
2.Webサービス/デジタルプロダクトの継続改善
SaaSやアプリなど、リリース後も頻繁にアップデートできるプロダクトでは、
リーンは今でも主力の手法です。
A/Bテストやアクセス解析と組み合わせることで、ユーザー行動から学習するサイクルが回しやすくなります。
3.ニッチ市場・セミオーダーメイド製品の検証
大手が参入しにくいニッチ市場や小規模市場では、
少数ユーザーでの検証でも十分な学びが得られます。
私も過去に、社内向けに特化したワークフロー改善ツールを試作したとき、
ユーザー5人からのフィードバックで主要課題の8割を発見できました。
4.将来ニーズが読めない新興分野での探索
生成AIやWeb3など、未来のユーザー像がまだ固まっていない分野では、
完璧な計画を立てても外れる可能性が高いです。
こうした領域では、リーンの「早く出して学ぶ」アプローチがむしろ強みとなります。



このように、リーンスタートアップは「低リスクで学習できる環境」や「変化の激しい市場」では今でも有効です。
次の章では、実際の日本企業やスタートアップでの成功・失敗事例を紹介し、リーンの現実的な評価を見ていきます。
日本スタートアップ&企業内PMの実践事例と評価
リーンスタートアップは、日本でも多くのスタートアップや企業内新規事業で試されています。
ここでは、成功事例・失敗事例・私自身の体験談を交えて、実務での評価を整理します。
1.スタートアップでの成功事例:小規模MVPで市場をつかんだ例
ある国内のBtoB SaaSスタートアップでは、正式版開発に入る前に、
スプレッドシート+簡易フォームだけのMVPを作り、顧客10社に限定提供しました。
結果、初期の3社が正式契約に進み、開発投資のリスクを大幅に下げることができました。
この事例のポイントは、ユーザーが価値を感じる最小単位を正しく見極めたことです。
派手な機能は不要でも、課題解決の核さえ満たせばリーンは効果を発揮します。
2.企業内新規事業での失敗事例:品質問題で逆効果に
一方、企業内の新規事業で「まずは小さく出そう」とした結果、
未完成のプロトタイプが社内でネガティブに受け止められた事例もあります。
私自身もこの状況を経験しました。
社内向けの業務改善ツールをMVPとしてリリースしたものの、
UIが荒く、動作も不安定だったため、「使いにくいツール」という印象が先に広まってしまったのです。
改善版を出しても、最初の印象を覆すのに時間がかかりました。
この経験から学んだのは、クローズド環境でも最低限のUX・安定性は必須ということです。
3.現場での評価:リーンは「武器になるが万能ではない」
これらの事例から見えてくるのは、リーンスタートアップは今でも強力な武器になり得ますが、
- 初期品質の担保
- 実験範囲の明確化
- 成功基準の共有
といった前提条件がないと、逆効果になる可能性もあるということです。
次の章では、こうした学びを踏まえて、2025年のリーン実践に使えるチェックリストを紹介します。
2025年版 リーンスタートアップ実践チェックリスト


リーンスタートアップは今でも強力な手法ですが、2025年の市場環境では、
慎重な適用と事前準備が成功のカギです。
ここでは、実務で活用する際に確認したいチェックポイントをまとめました。
チェックリスト:実施前に確認すべき6つのポイント
- ターゲット顧客を明確にしたか?
- どのユーザーに試してもらうのかを具体的に決める
- 社内テストや限定リリースなど、クローズドで始められると安全
- 最小限の価値(MVP)を特定できているか?
- 何を検証するために出すのかを明確化
- 機能は「価値を伝える最小限」に絞る
- 初期品質とUXは最低限クリアしているか?
- 動作の安定性・使いやすさは必要最低限確保
- SNS時代はネガティブな印象が広まりやすいため注意
- 学習サイクル(Build-Measure-Learn)を短期間で回せるか?
- 検証後すぐに改善に着手できる体制を用意する
- 社内・ステークホルダーの期待を調整できているか?
- 「これは実験段階」と共有し、早期の失敗を許容してもらう
- 終了条件・成功基準を事前に決めているか?
- 続けるか、ピボットするかの判断基準を明確にする
私の実務での学び
以前、社内向けの業務改善ツールをリーンで検証した際、
「社内だから少し荒くても大丈夫だろう」と思って出したMVPが逆効果になりました。
初期の印象を覆すのは大変で、品質ラインをどこまで確保するかの判断が肝心だと痛感しました。
このチェックリストを押さえて実践すれば、
リーンスタートアップは2025年でも学習速度を最大化する強力なフレームワークとして活用できます。
まとめ|リーンスタートアップは「選んで使う時代」へ
この記事では、リーンスタートアップが「時代遅れ」と言われる理由と、
それでも2025年でも有効な場面や実践のコツを解説しました。
この記事で押さえておきたいポイント
- リーンは短期学習には強いが、競争激化や品質要求が高い市場では不利になる
- いまでも有効なのは「クローズド環境」「変化が激しい市場」「小規模検証が可能な領域」
- 実践する際は、品質ライン・学習サイクル・ステークホルダー調整が成功のカギ
- 2025年は「なんでもリーン」ではなく、場面を選んで活用することが重要
私自身、社内PMとしてリーンを試し、失敗も成功も経験しました。
実務で学んだのは、リーンは万能ではないが、うまくハマると強力な武器になるということです。
初心者PMの方へ:
リーンスタートアップは、正しく使えば学びのスピードを加速させる最高のフレームワークです。
まずは小さく安全に試せる領域から一歩を踏み出してみてください。
その一歩が、次の大きな成果につながります。
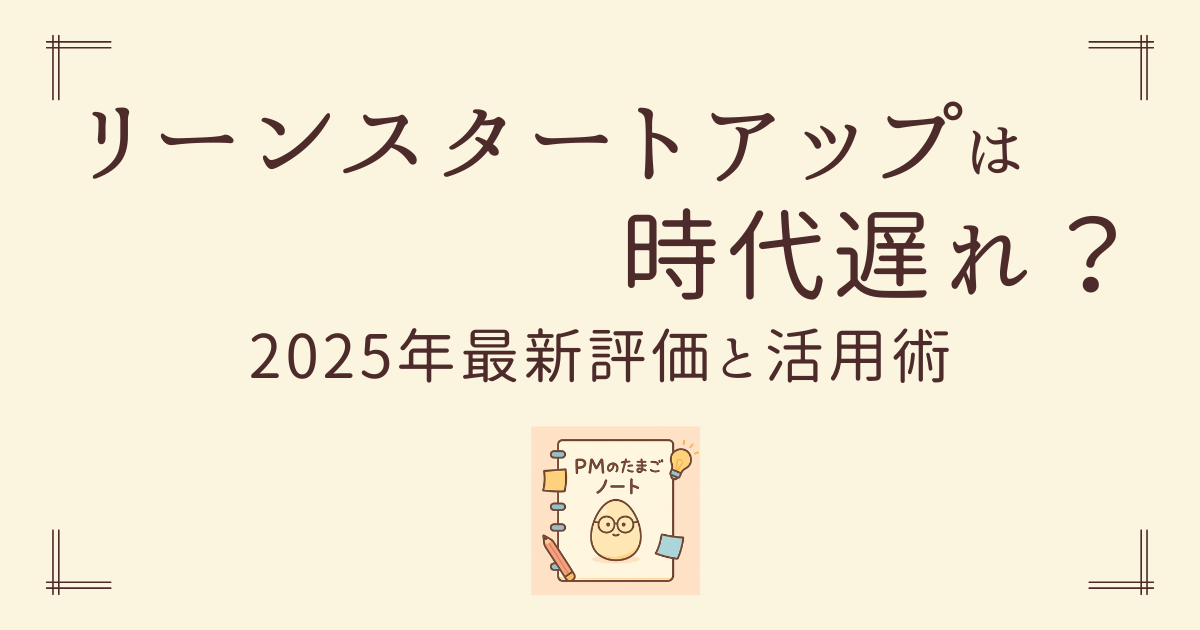
コメント